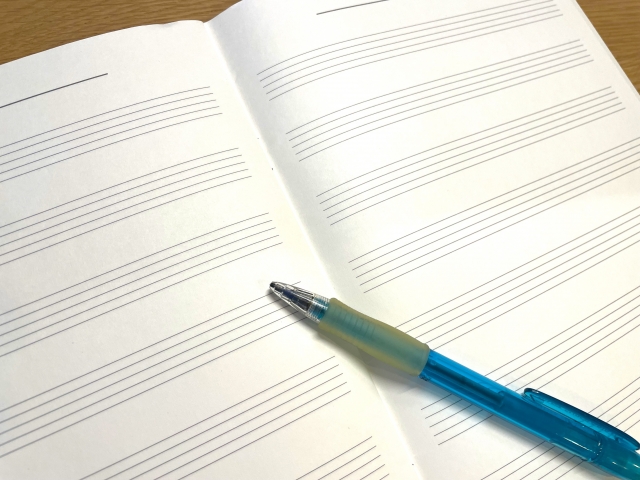こんにちは!音大受験アカデミー講師の田淵羽音です。
本記事では、藝大をはじめ、さまざまな音大受験の試験科目として設定されている「ソルフェージュ」の対策について、私自身の体験談をもとに、僭越ながらアドバイスをお伝えしていければと思います。
1. はじめに
音大受験の対策で、避けては通れないのがこの「ソルフェージュ」という科目。
では、具体的に「ソルフェージュ」とはどのような科目なのでしょうか?
ソルフェージュは簡潔に言うと「音楽の基礎を固める」ことを目的としたものです。
私たちは新しい言語を習得するとき、文法やボキャブラリー、発音などをしっかり学びながら、徐々にその言語に慣れていきます。その先には、リーディングやリスニング、ライティングやスピーキングなど4技能をバランス良く鍛えていくという流れがあります。
音楽だって、同じ道を辿るべきです。
「音」を認識して、その音ひとつひとつに「ドレミファソラシド」と名前をつけていき、それをどのように組み立てて音楽が作られていくかを学び、楽譜の読み方や書き方を習得する。その前段階が完了したら、実際に楽譜を読んで頭の中で音楽を流したり、聴き取った音楽を楽譜に書き写したりと、より実践的な学習へと移行していく。
このようなプロセスこそが、総合的な能力が備わる「音楽家」への第一歩となるのです。
これが「ソルフェージュ」の考え方になります。
前述の通り、ソルフェージュは音楽にまつわる総合的な能力を育成する科目です。
そのため、音大入試のソルフェージュという科目には、分野ごとに細かい試験が設けられています。
2. 藝大入試におけるソルフェージュ試験の概要
大学によってソルフェージュの試験内容は少しずつ違います。そのため、本記事では東京藝術大学音楽学部の「基礎能力検査」を参考に、ソルフェージュの中でも最も重要な「聴音」「新曲視唱」「リズム課題」の3科目についてお伝えします。
① 聴音
聴音とは、ピアノで演奏された旋律を聴き取って、正確に楽譜に書き取るというものです。最初は、単旋律の問題から始まり、二声の複旋律聴音、四声の和声聴音の問題へと続きます。また余談ですが、令和8年度入試より、単旋律が記憶聴音の課題へと変更されることが予告されています。より高度で実践的な能力が求められるようになっていますね。
② 新曲視唱
新曲視唱では、短い時間の中で初見の楽譜を読んで、音程をつけながら楽譜どおりに歌うことが求められます。つまり、楽器を使うことなく自分の中で音楽を響かせることができるかが問われる科目になります。
③ リズム課題
リズム課題は、指揮を振ったり手で拍子を取ったりしながら、楽譜に書いてある旋律を、音程をつけずに音名を口ずさむテストで、リズムの正確さを評価される科目になります。
3. 筆者とソルフェージュ
ここまでソルフェージュの意義や詳細を説明してきましたが、この記事を書いている当の私はと言いますと、昔からソルフェージュに強い苦手意識がありました。
私とソルフェージュとの出会いは今から13年前、小学1年生の頃まで遡ります。
私は幼少の頃から音楽大学附属の音楽教室に通っていたため、通常の受験生よりも随分と早い時期から、カリキュラムの一環としてソルフェージュに取り組んでいました。
このような英才教育を長い間受けていたのですから、この人はソルフェージュなんて朝飯前なんだろうなぁと思ったそこのあなた!
甘いです。
いや、甘いのは間違いなく私のソルフェージュ能力なのですが、とにかく本当にソルフェージュに苦しめられてきた人生でした。皆と同じ音を聴いているはずなのに、私だけ何の音が鳴っているかが分からず、ただ鉛筆を動かすフリをしていた小学生時代、聴音をいつも一番に書き終える女の子に、「なんでそんなに書けるの?」と恥を忍んで聞いてみたことがあります。すると、返ってきた答えは単純明快なものでした。
「え、聞こえてきた音を書いているだけだよ?」
頭がガツンと殴られた気分でした。
小学生の私の前に立ちはだかったのが「絶対音感」の壁だったのです。
それからは、「絶対音感が無いから無理だよなぁ」と諦めて、ソルフェージュの時間は目立たないようにじっと座っているのがお決まりになっていきました。
転機となったのは、高校1年秋の聴音の試験です。
私は既に、藝大の楽理科に進学したいという気持ちが固まっていたので、そろそろしっかりと聴音の対策をしないとなぁと思っていた矢先、返ってきた答案に書いてあった点数は、28点。ショックで視界が滲む帰り道、私はソルフェージュへの姿勢を180° 変えることを誓ったのです。
4. 絶対音感なしの聴音対策とは
とはいえ、やる気を出したからって突然音が聴き取れるようになるわけではありません。途方に暮れて、当時師事していたソルフェージュの先生に泣きつくと、いつも優しい先生から「あなたに足りないのは、絶対音感だけではなくて『音感』かもね。」と厳しい一言が。
思い返せば、私はピアノを弾く時も、楽譜の形や鍵盤の位置で音を把握していたし、他者の演奏を聴くことも、自分の中で一度歌ってみることもなく、ただガムシャラにピアノを弾くだけの演奏をしていました。ただピアノの鍵盤を押すだけでは「音感」は養われないということなのです。
私の問題は「絶対音感」が無いことではなく、「音感」が足りなかったこと。
この事実に気が付いてから、私が実際に行なって効果的だと思った「音感」を養うソルフェージュ対策をいくつかご紹介します。
① 聴音課題を自分で歌ってみる
聴音課題は本来、誰かにピアノで弾いてもらって書き取るものですが、その課題がすべて終わった後に、正解の旋律を自分で歌ってみると、例えば7度(ド〜シなど)の音程はこれくらいの幅なのかと何となく身に付いていきます(これは聴音だけでなく新曲視唱にも活かせます!)。また、聴音の課題はあくまで試験問題です。つまり、独創性は追求されてないので、問題同士が似ることはよくあります。ぜひ、聴音課題を歌ってよく出題されるパターンを覚えていってください。
② メロディーラインを記憶する
来年度から藝大には記憶聴音の問題が追加されますが、まさにその能力を他の聴音課題にも活かすことができます。速いパッセージの旋律や、複雑な二声の課題は、聴音が苦手な人は即座に書き取るのが難しいかと思います。そのため、直前に弾かれた旋律を常に頭の中に鳴らしておき、それをインターバルの時間に書けるように、メロディーラインを記憶できるようにしておくと良いでしょう。
③ 和声の基礎知識をつける
和声とは、和音と和音を結びつける約束事のことです。例えば、基本的には、Ⅴの和音(C-durならソシレ)は、Ⅰの和音(ドミソ)かⅥの和音(ラドミ)にしか進めない約束になっています。和声の知識があれば、次の和音が予想できるようになるので、和声聴音に苦手意識がある方には特におすすめです。
5. ソルフェージュが得意になるために
絶対音感があれば、ソルフェージュ対策が捗ることには間違いありません。しかし、それ以上に大切なのは「音感」自体です。この「音感」という能力は、才能に依拠するものではなく、自分に合う対策や勉強によって身に付けることができる地道な努力の産物です。今、ソルフェージュに苦手意識がある方は、ぜひ一度、自分の「音」に対する向き合い方を振り返ってみると良いかもしれません。
6. ソルフェージュ対策をオンラインレッスンで!
そうは言っても、自分ではどのように対策すれば分からない…という方もいらっしゃるかと思います。
音大受験アカデミーでは、実際に藝大や音大受験を突破した講師によるソルフェージュのレッスンを完全オンラインで受講することができます。
マンツーマンのレッスンの中で、個々のレベル感に合わせて最適な入試対策を提案いたします。無料入会面談・体験レッスンなども随時行なっていますので、お気軽にこちらからお問い合わせください!
執筆:田淵羽音 監修:矢野葵